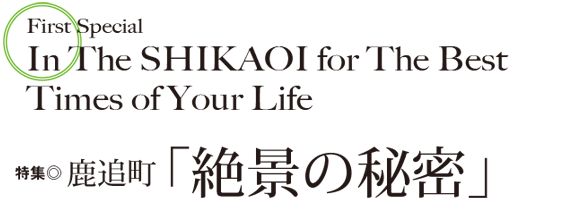
30 万年前に始まった火山活動によって、川がせき止められて誕生した然別湖。街の中心地から然別湖へと続く道沿いには夏でも解けない氷を含む永久凍土があり、冷たい風を吹き出す北極圏とよく似た風穴の森が育まれました。そこには、生物の遺伝子の宝庫と呼べるような多種多様な命が息づく生態系が広がっています。小さなエリアに凝縮された鹿追町の貴重な自然と特異な地形が、日本で指折りの絶景地を生み出しているのです。
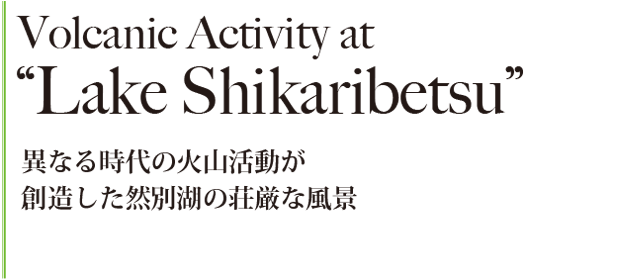
街の中心部から道道85号鹿追糖平(ぬかびら)線を北上すれば、鹿追町が誇る絶景のひとつ、然別湖に到着します。然別湖は、北海道のほぼ真ん中に位置し、大雪山国立公園内で唯一の自然湖です。北海道で最も標高の高い湖で、標高は約800m。日本国内でトップクラスの透明度を誇ります。湖を囲むようにそびえる美しい山々は、およそ30万年前から始まった火山活動によって、異なる時代に誕生しました。南ペトウトル山と北ペトウトル山(旧期然別火山群)は、原生人類の起源とされる年代と同じ頃、約30~10万年前の火山活動によってつくられた山です。その後、約6千~1万年前の火山活動により、西ヌプカウシヌプリ、東ヌプカウシヌプリ、白雲山、天望山が形成され、北部ヤンベツ川をせき止める形で然別湖ができました。
この天然のダム湖ができたことで、ヤンベツ川に生息していたオショロコマ(低水温を好むイワナの仲間)が然別湖に陸封されて独自の進化を遂げ、美しい体色をまとう固有種のミヤベイワナが誕生したのです。ミヤベイワナは、河川より少ない水生昆虫や陸生昆虫の環境下でプランクトンを多く捕食するようになったため、他のオショロコマよりプランクトンをこしとる器官、鰓さ いは耙の本数が多いのが特徴です。体高が高くヒレも長く大きく、さらに体色が生息場所によって変化するため、個性豊かな姿を見せてくれます。湖の底石や湖水の色によって、ブラウン、グリーン、ブルーなどのきらめきをベースに、ピンクやオレンジの斑点が浮かぶ魚体は、まさに湖の宝石です。多種多様な命がいたるところで輝き、一日として同じ風景に出会わない然別湖の景色は、まさに悠久の時間が創り出す絶景といえるでしょう。
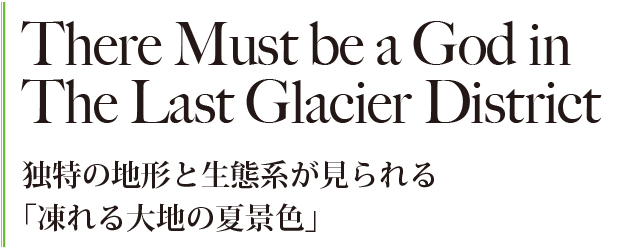
然別湖周辺の山には、日本最大級の広さを誇る風穴地帯があります。風穴とは、岩の隙間から冷たい風が吹き出る場所のことで、森に点在する風穴からは、冬の寒さを閉じ込めた地下の天然の冷蔵庫から、冷たい風が吹き出ています。風穴地帯の岩の隙間に手を伸ばせば、真夏でも低いときには2℃ほどの冷気を、はっきり感じることができるでしょう。
然別風穴地帯の地下には、春に雪が解けても地面は氷点下のまま解けることなく成長を続けた、日本最古の永久凍土も見つかっています。標高は1,000~1,200mとあまり高くはないのですが高山植物を見ることができ、澄んだ声で「ピィッ、ピィッ!」と鳴く鹿追町のマスコット的存在、体長15cmほどのナキウサギが生息できるのも、風穴の冷気のおかげです。この森では、然別風穴地帯ならではの神秘的な姿、特異な自然風景を目にすることができます。

十勝平野北部に位置する鹿追町は、初夏から夏の終わりにかけて、早朝から昼前まで霧に包まれることがあります。日中に温められた水分を多く含む大地の空気が、夜半から朝にかけて然別湖方面から降りてくる冷たい空気に触れ、広い範囲で霧が発生するためです。朝、街で目を覚まして「今日は曇り空かな」と思っても、道道85号鹿追糖平線を然別湖方面へ向かってみてください。わずかに高度を上げただけで景色は一変し、霧が晴れて雲海が広がっているかもしれません。
雄大な十勝平野を一望できるビューポイント「扇ヶ原展望台」から南を眺めれば、十勝平野全体が霧にすっぽりと覆われ、南西側には日高山脈の峰々がそびえる、圧倒的な絶景を見ることができます。こうした美しい霧の発生により夏の気温上昇が和らぎ、鹿追町の農地に大切な水分が供給され、大地と人々が潤されます。そして、湿度を含んだ霧は、然別川上流部へ続く河畔林にも影響を与え、森の生き物たちが夏場、健やかに暮らしていける環境も整えてくれるのです。霧に誘われるがまま散策すれば、然別川沿いの川面にも霧が現れ、おとぎ話のような幻想的な風景の中で草をはむエゾシカの親子や動物たちに出会えるかもしれません。旅先で霧が出ると少しがっかりするかもしれませんが、鹿追町の濃い霧の先には、多様な自然の世界が創る、美しい風景が広がっているのです